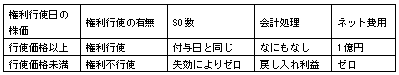失効した場合の費用計上の必要性
ストックオプション取引において、その費用は見かけ上の費用であり、減価償却と同様キャッシュの流出はありません。それが原因かどうかは分かりませんが、ストックオプション会計基準での費用計上のしかたは、金融商品として市場で取引されるオプションの費用処理とはかなりかけ離れています。
ストックオプションの場合は、取引が完結して付与されたストックオプションの権利が確定しても、株価の低迷などにより権利不行使のまま失効した場合は、費用計上は発生しません。(具体的には失効による利益は、原則として特別利益に計上することになります。)しかし、考えてみれば、ストックオプションの対価として、労働サービスを提供した従業員等にとってみればタダ働きとなり、会社から見れば無償でサービスの提供を受けたことになります。
通常のオプション取引では、買い手は一度支払ったオプション料は権利行使の是非にかかわらず返却されることはありません。
そもそも、オプション取引から期待される利益は、将来の株価の上昇のみからもたらされるものではなく、将来の株価の変動性からも、もたらされます。
この意味では、失効数の利益参入(費用非計上)はオプション理論上受け入れにくいものに映ります。
例えば、ストックオプションの発行した企業の株価がその後一進一退を繰り返し、権利行使日が到来したときは丁度行使価格と同じレベルに推移していたとします。発行時の公正な評価額評価額は1億円として、現時点では失効数はゼロとします。もしストックオプションの取得者が合理的な市場参加者だとしたら、彼らの行動と企業の会計上の処理は以下の通りとなります。
このように、現在の会計基準では権利行使時における株価水準が変わらなくても権利行使するか否かで、費用への影響が大きく変わってきます。極端なケースでは100か0(All or Nothing)となることもありえます。
(参考:ストック・オプション会計評価と評価の実務 税務研究会出版局)
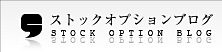
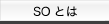

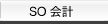

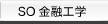
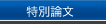

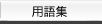
 ← 詳細はこちら
← 詳細はこちら